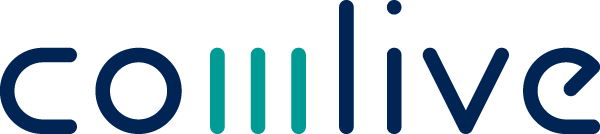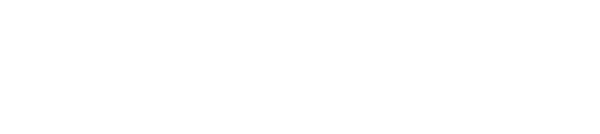「Web」と「セミナー」を組み合わせた言葉が「ウェビナー」です。ウェビナーはオンライン上で行われるセミナーのことであり、幅広い顧客層にリーチできる手段として多くの企業が開催しています。そして、ウェビナーの開催方法のひとつとして「擬似ライブ配信」が注目されるようになりました。この記事では、擬似ライブ配信のメリットや事例などを解説します。
- あらかじめ収録した映像を配信する
- メリット
- 不特定多数に見せる場合は向かない
- リアルタイムでスタッフが動かなければならない
- 動画制作のスキルが必須
- 弁護士ドットコム株式会社
- 株式会社ブレインパッド
- 住友化学園芸株式会社
ウェビナーの疑似ライブ配信とは?どのようなメリットがあるか
オフラインのセミナーではリアルタイムで参加者と主催者がコミュニケーションをとる方式が当たり前でした。しかし、ウェビナーではさまざまな配信方法を選べます。この段落では、ウェビナーの疑似ライブ配信を説明していきます。
stopあらかじめ収録した映像を配信する
疑似ライブ配信とは、あらかじめ主催者が収録しておいた動画を配信する手法です。あるいは、一度開催したライブ配信ウェビナーの動画を再度配信します。そのうえで、疑似ライブ配信では、視聴者からのチャットや音声といったコミュニケーションツールを残しています。つまり、動画自体は収録したものであっても、視聴者とのコミュニケーションはリアルタイムで行われるのです。
stopメリット
ライブ配信と比較したとき、疑似ライブ配信のメリットとなるのが「確実性」です。本物のライブでは予想外のトラブルが起こる可能性もあります。たとえば、機材が不調だったとすれば貴重なウェビナーの時間が奪われてしまいます。視聴者からの印象も悪いでしょう。疑似ライブ配信ならリアルタイムでよくあるトラブルを避けられ、視聴者にしっかりと内容を見てもらいやすくなります。
それでいて、疑似ライブ配信では「即時性」も確保されます。オンデマンドでは視聴者が好きなときに動画を見られるものの、その場で質問や意見を投げかけることはできません。コミュニケーションが機能していないので、視聴者のロイヤリティを育みにくいのです。疑似ライブ配信は、リアルタイムで視聴者とコミュニケーション可能です。視聴者の声にすぐ反応でき、満足度を高めてもらいやすくなります。
純粋なライブではないので、主催側はタイムキープやプロジェクターの操作など、進行に集中を削がれることもありません。オンデマンドのように、編集にもこだわれます。ライブで配信したときの反応を踏まえ、強調したい部分を切り抜くような編集もできます。ライブ配信とオンデマンド配信の長所を兼ね備えたのが疑似ライブ配信だといえるでしょう。そのほか、コスト面も疑似ライブ配信の大きなメリットです。ネット環境と機材さえあれば、疑似ライブ配信には会場費がかかりません。オフィスで収録した動画を配信しても、充実したウェビナーになりえます。
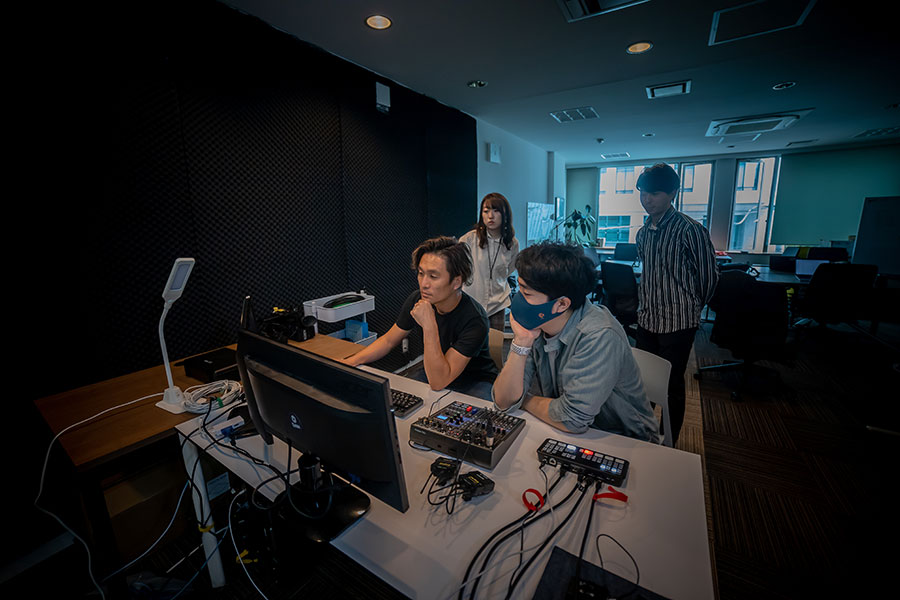
疑似ライブ配信の課題!実際に開催するときは何に注意する?
魅力の多い擬似ライブ配信も、課題がまったくないわけではありません。以下、疑似ライブ配信でウェビナーを開催するときの注意点について解説します。
stop不特定多数に見せる場合は向かない
あくまでも疑似ライブ配信は、リアルタイムの視聴者に向けた手法です。基本的には、動画がアーカイブ化されるわけではありません。配信された動画は視聴者に再生できなくなります。つまり、不特定多数のネットユーザーにずっと見てもらいたいウェビナーを配信する場合には、疑似ライブ配信は向きません。そのかわり、ウェビナーの視聴者があらかじめ決まっているケースでは大きな問題はないといえます。
stopリアルタイムでスタッフが動かなければならない
実際に疑似ライブ配信を行うとき、スタッフは必ず待機しなければなりません。なぜなら、視聴者から投げかけられるコメントに対応しなくてはならないからです。「担当者が当日不在でもウェビナーを配信したい」という目的には、疑似ライブ配信は応えにくいでしょう。ただ、リアルタイムでのコミュニケーションを求めているならむしろ、適した手法のひとつです。
stop動画制作のスキルが必須
一度収録した動画を配信するので、疑似ライブ配信では編集や演出が必須です。そのためのスタッフを雇い、動画を配信できる形にしなければなりません。しかし、肯定的に捉えるなら、視聴者が見やすい状態でウェビナーを配信できるともいえます。多少手はかかっても、要点を明確に伝えられる動画にしたい場合に疑似ライブ配信はぴったりでしょう。
企業はどのように開催してきた?疑似ライブ配信によるウェビナーの事例!
疑似ライブ配信によるウェビナーは、多くの企業が実践しています。ここからは、疑似ライブ配信の事例を挙げていきます。
stop弁護士ドットコム株式会社
法律ポータルサイトの運営で知られている企業です。弁護士ドットコムでは定期的にセミナーをオフラインで開催していたものの、新型コロナウイルス感染拡大後は難しくなってしまいました。また、地方でも「セミナーに参加したい」という声が大きくなっていきます。そこで、弁護士ドットコムは疑似ライブ配信によるウェビナー開催に踏み切りました。
疑似ライブ配信を希望したのは、通信の安定性を望んだからです。ライブ配信の経験が少ない中、中継中のトラブルに対応できるかどうかは主催側の不安でした。そこで、あらかじめ収録した映像を配信できる、疑似ライブ配信を選択しました。開催時にはオフラインセミナーの約2倍が参加し、大きな反響を呼んでいます。
stop株式会社ブレインパッド
データ活用による企業の経営改善を提案してきた株式会社ブレインパッドも、疑似ライブ配信によるウェビナーを開催しています。新型コロナウイルスの影響で集客型のセミナーが難しくなったころ、ブレインパッドではウェビナーへの切り替えを検討し始めました。しかし、ライブ配信を行うには人手が少なく、機材トラブルへの不安もありました。そこで、ブレインパッドは疑似ライブ配信でのウェビナーを選びます。少人数でも定期的に開催できる疑似ライブ配信により、ブレインパッドは月15件ほどのウェビナーを開催しています。
試行錯誤しながら始めた疑似ライブ配信も、視聴者数は当初の4倍にまで増えました。さらに、視聴後のアポ獲得率は集客型セミナーと変わらない数字になっています。
stop住友化学園芸株式会社
園芸の専門家として、住友化学園芸株式会社は全国のホームセンター、園芸店向けにセミナーを開催してきました。一方で、集客型セミナーの費用をいかに削減するかが企業の課題にもなっていました。そこで、住友化学園芸は疑似ライブ配信によるウェビナーを開始します。会場費や遠征費のかからないウェビナーなら、地方の顧客にも低コストで講習を行えます。さらに、チャットツールで参加者とコミュニケーションをとることで、質疑応答も盛り上がりました。疑似ライブ配信によって本社から離れた顧客ともつながれたうえ、中継のトラブルも避けることができました。

事例を参考にして擬似ライブ配信!ウェビナー開催で新たな集客を
ウェビナーを検討しているなら、擬似ライブ配信がおすすめです。配信時のトラブルを避けられるだけでなく、参加者とのコミュニケーションも行えるからです。事例を見ても、疑似ライブ配信によって集客に成功した企業は少なくありません。今までアプローチできなかった顧客層に出会えるのも疑似ライブ配信の大きな魅力だといえるでしょう。